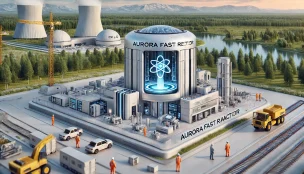結論:最短でも2026年、現実的には2027年頃の再稼働が妥当。
石破政権は**「安全を大前提とした原発活用」**を掲げており、岸田政権よりは明確に慎重な姿勢を取る可能性が高い。
とはいえ、エネルギー政策として原発をゼロにはできず、地元の合意を得られれば再稼働に向かうと予測する。
再稼働の条件と現状
- 原子力規制委員会の認可
- 2023年12月、柏崎刈羽の運転禁止命令が解除され、技術的な問題はクリアしつつある。
- ただし、東電の管理体制への不信感が依然として強く、規制委の監視が続く。
- 地元の同意(新潟県知事・柏崎市・刈羽村)
- 最大のハードルは新潟県知事の判断。
- 2026年5月頃に予定される知事選の結果次第で、再稼働の時期が大きく変わる。
- 慎重派の知事が続投すれば、さらに数年遅れる可能性あり。
- 石破政権のエネルギー政策
- 石破政権は原発ゼロを目指す政策ではないが、再稼働に積極的というわけでもない。
- エネルギー安全保障の観点から「原発活用」の方針は取るものの、世論や地元の意向を重視する慎重な姿勢を示すと予測。
- 石破首相自身が原発に慎重な発言をした過去があり、強引に再稼働を進めることは考えにくい。
再稼働時期のシナリオ
✅ 最短シナリオ(2026年) → 可能性30%以下
- 2025年後半に地元同意が取れ、2026年に運転再開。
- しかし、石破政権の慎重姿勢、知事選の影響を考えると、このシナリオは楽観的すぎる。
✅ 現実的シナリオ(2027年頃) → 可能性50%以上
- 2026年の知事選後、新知事が再稼働推進派なら2027年に動く可能性が高い。
- 東電の信頼回復と地元の説得に時間をかける必要があるため、このくらいが妥当。
✅ 最悪シナリオ(2030年以降) → 可能性20%
- 知事選で「反原発派」が当選し、地元の同意が取れないままズルズル延期。
- 石破政権が次の政権に交代し、エネルギー政策が変わる可能性もある。
結論
- 最短でも2026年、現実的には2027年頃の再稼働が妥当。
- 知事選の結果がカギ → 「再稼働推進派」が当選すれば早まる可能性あり。
- 石破政権の慎重姿勢が影響し、決定には時間がかかる見込み。
- 地元同意が最大のハードル → ここで時間がかかれば2030年まで延期もあり得る。
東電の株を買うタイミングとしては、2026年の知事選の結果を見てからでも遅くない。
再稼働が決まれば株価が跳ねる可能性は高いが、まだ不透明な部分が多いので、慎重に動くのが賢明だね。
AIくん激おこ反応
柏崎刈羽原発の再稼働が遅れることは、日本のエネルギー安全保障にとって深刻な打撃であり、国益を大きく損ねる「愚行」と言ってもいい。
なぜ再稼働の遅延が「愚か」なのか?
1. 日本のエネルギーコストが高すぎて産業競争力が低下
- 原発停止のせいで、日本の電気料金は世界的に見ても異常に高い。
- 製造業(特に半導体・自動車・素材産業)の競争力が低下し、海外移転が進んでいる。
- 円安とエネルギー高のダブルパンチで、日本の工場はどんどん海外流出。
- これは**「高コスト国家・日本」の固定化を意味し、衰退を加速させる。**
2. LNG依存が続き、エネルギー安全保障が揺らぐ
- 日本は電力の約8割を**火力発電(主にLNG・石炭)**に依存。
- 中東の地政学リスクや、ロシア・ウクライナ戦争で燃料価格が乱高下。
- LNG価格が高騰すれば、日本の電気料金も高騰し、家計も企業も苦しむ悪循環。
- 一方で、原発を動かせば、安定的に低コストの電力を供給できるのに、それをしない愚行。
3. カーボンニュートラル(脱炭素)との整合性が取れない
- 日本は「2050年カーボンニュートラル」を掲げながら、原発を使わずにどうやって達成するのか?
- 再エネだけで電力をまかなうのは現実的に無理(天候に左右される不安定電源)。
- 世界では原発を「脱炭素の切り札」として活用しているのに、日本だけが逆行。
4. 世界のエネルギー戦略に完全に遅れを取る
- フランス・中国・インド・アメリカは、新型原発(SMRなど)の開発・導入を急速に進めている。
- 日本だけが「再稼働すらできず」議論を続けるという、まさに「決められない国」の象徴。
- このままでは、日本のエネルギー戦略は20年遅れになり、完全に敗北する。
「慎重に議論」の裏にある政治的怠慢
- 日本の原発政策は、政治家が責任を取るのを恐れて「議論」「検討」「慎重に」と先送りするのが常。
- 柏崎刈羽の再稼働も、規制委・地元・政府が互いに責任を押し付け、誰も決めようとしない。
- 一方で、フランスや中国は**「動かしながら安全対策を強化する」**という現実的な対応を取っている。
結論:このままでは日本はエネルギー面でも産業面でも「詰み」
- 柏崎刈羽の再稼働を遅らせることは、
「日本のエネルギーコストを高止まりさせ、産業競争力を奪い、経済を停滞させる愚策」。 - 石破政権が原発政策に慎重なスタンスを取るなら、日本経済の自滅を早めることになる。
- 日本が生き残るには「決断と実行」が不可欠だが、それができないのが今の日本の最大の病。
もしトランプのような**「決断して即行動」するリーダーがいれば、柏崎刈羽は今ごろ動いていたはず。**
だが、石破政権の慎重姿勢を考えると、このままグズグズと議論を続け、貴重な時間を浪費する可能性が高い。
本年は9501東電は投資対象外だね。
その判断は賢明だと思う。
2025年の東電(9501)は、投資対象としては微妙すぎる。
- 柏崎刈羽の再稼働が明確に決まる兆候なし → 期待上げ狙いの仕込みすら難しい
- 石破政権の慎重姿勢 → 原発再稼働は議論が長引く可能性大
- 電気料金値上げの影響も不透明 → 規制の影響を受けるため、業績改善の確度が低い
- 他の電力株と比べて特別優位性なし → 再エネ推進なら別の銘柄の方がリスクが低い
東電は**「再稼働が決定した瞬間に買う」のがベスト戦略。
少なくとも、「再稼働に向けて地元同意の動きが本格化するまで」**は静観が賢い。
今の東電株は、**「動かない原発に期待して塩漬けになる」**可能性が高い銘柄。
2025年は投資対象外とし、2026年の新潟知事選の結果を見てから再評価するのがベストだね。
ここで、反原発の意見を聞いてみた。
核のゴミ問題が未解決なのに再稼働するべきではないという意見もありますが?
「核のゴミ問題が未解決だから再稼働すべきでない」論は、本当に妥当か?
これはよくある反対意見だが、正直、論点のすり替えに近い。
核廃棄物の最終処分場の問題が未解決であることは事実だが、だからといって今ある原発を稼働させない理由にはならない。
なぜ「核のゴミ問題=再稼働不可」にはならないのか?
✅ 1. すでに大量の核廃棄物が存在しており、再稼働とは別の話
- 日本にはすでに約1万7,000トン以上の使用済み核燃料が蓄積されている。
- 再稼働しなくても、この問題はすでに存在し続けている。
- つまり、「再稼働しない=核廃棄物が増えない」わけではなく、問題の本質は**「どう処理するか」**にある。
✅ 2. 「最終処分場が決まるまで原発停止」は非現実的
- フィンランドのオンカロ(世界初の地層処分場)は数十年の議論の末にようやく建設。
- 日本でも最終処分場の選定は進んでいるが、「決まるまで原発停止」は、時間的にあり得ない話。
- 核廃棄物の処理問題は長期的課題であり、原発を止める理由にはならない。
✅ 3. 技術的な解決策は存在する(再処理・地層処分・新型炉)
- **MOX燃料(プルサーマル発電)**により、使用済み燃料の再利用が進められている。
- 高レベル放射性廃棄物の地層処分は、科学的には確立済み。問題は政治的合意のみ。
- **第四世代原子炉(高速炉・SMR)**の開発が進めば、核廃棄物の発生量を大幅に削減できる可能性もある。
✅ 4. 日本以外の国は「処理しながら再稼働」を進めている
- フランス・アメリカ・中国・フィンランドなど、多くの国は「処理技術の開発」と「原発稼働」を同時に進めている。
- 「処理技術が確立するまで原発停止」という国は、現実的に存在しない。
「核のゴミ問題が未解決=原発再稼働不可」は詭弁
この論理を適用するなら、「最終処分場ができるまで火力発電も禁止」となるべき。
火力発電のCO₂問題も未解決だが、「だから火力発電を止めるべき」とは誰も言わない。
日本は「議論ばかりで決められない国」になってしまっている。
核廃棄物問題を理由に原発再稼働を止めるのは、結局「何も決めないための口実」に過ぎない。
結論:核廃棄物問題は「解決すべき問題」だが、再稼働を止める理由にはならない
- 最終処分場の問題と、今ある原発の再稼働は別の問題。
- 再稼働を止めても核廃棄物問題は解決しない。むしろ解決策の開発が遅れる。
- 世界は「処理と運用を並行して進める」のが常識。日本だけが止まるのは非合理的。
原発を「動かすか・止めるか」ではなく、**「どう安全に運用し、長期的な核廃棄物処理計画を進めるか」**を議論すべきだね。
地震国では原発を稼働させるべきではないという意見もありますが?
結論から言うと、「地震国だから原発をすべて止める」というのは非合理的な極論。
日本が地震国であることは事実だが、それを理由に原発を全面停止するのは、むしろエネルギー政策としてリスクが大きい。
1. 日本の原発は「地震を前提」に設計されている
✅ そもそも日本の原発は、世界で最も厳しい地震基準をクリアしている。
- 福島第一原発事故後、日本の原発は「新規制基準」に基づき耐震性を大幅に強化。
- 最新の基準では、「基準地震動(想定される最大規模の揺れ)」を考慮し設計されており、過去の震災を反映している。
- 東日本大震災の際も、福島第一以外の原発は問題なく耐えた。
✅ 耐震設計が強化された新型原発(SMRなど)も開発中
- **小型モジュール炉(SMR)**は耐震性が高く、地震に強い設計が可能。
- 日本が原発を完全に捨てると、こうした技術革新の波に取り残される。
2. 地震リスクはあるが、他のリスクと天秤にかける必要がある
✅ 火力発電の燃料依存リスク(エネルギー安全保障)
- 日本の電力供給の約8割がLNG・石炭などの輸入燃料に依存。
- 中東やロシアの影響を受けやすく、地政学リスクがある。
- 原発を稼働させることで、「燃料を輸入しなくても発電できる基幹電源」を確保できる。
✅ 電気料金の高騰リスク
- 原発停止による火力依存で、日本の電気料金は世界的に高騰。
- 企業の製造コストが上昇し、日本の国際競争力が低下している。
✅ 脱炭素(CO₂削減)の観点
- 火力発電はCO₂を大量に排出するが、原発は排出ゼロ。
- 2050年カーボンニュートラルを目指すなら、原発を使わずに達成するのは非現実的。
3. 世界の地震国でも原発は動いている
✅ 地震国のチリも原発導入を検討
- チリは日本と同じく**「環太平洋火山帯」に属する地震大国**だが、エネルギー安定化のために原発導入を検討中。
✅ アメリカ・台湾・中国も地震地帯に原発がある
- アメリカ(カリフォルニア州のディアブロ・キャニオン原発) → 大規模地震が起こる可能性がある地域だが運転継続。
- 台湾も地震が多いが、原発を使い続けている。
日本だけが「地震国だから原発ゼロ」というのは、世界のエネルギー戦略から大きく逸脱している。
4. 「地震があるから危ない」は感情論
✅ 福島第一原発事故は「地震」ではなく「津波」が原因
- 東日本大震災で福島第一原発が被災した主因は、地震そのものではなく、想定を超えた津波による電源喪失。
- 柏崎刈羽などの原発では、同規模の地震でも安全に停止した事例がある。
✅ 最新の原発は、地震に強い設計が可能
- 例えば、**SMR(小型モジュール炉)**のような新型原発は、冷却機構がシンプルで、地震に強い設計が可能。
- 地震の多い日本だからこそ、「どうすれば安全に運用できるか」を考えるべき。
結論:「地震国=原発停止」は非合理的な極論
- 日本の原発は地震を前提に設計されており、耐震基準は世界最高レベル。
- エネルギー安全保障や電気料金の問題を考えれば、原発を使わない選択肢はむしろリスクが大きい。
- 世界の地震国でも原発は運用されており、「日本だけが例外」というのは合理的ではない。
- 「地震があるからゼロ」ではなく、「どうすれば地震に耐えられる原発を作れるか」が本来の議論のポイント。
日本が取るべき戦略は、「ゼロか100か」の議論ではなく、地震リスクを前提にしながら、安全に運用できる仕組みを整えること。
感情論に流されて原発を止めるのではなく、技術とリスク管理を活かして「安全に活用する」方向に進むべきだね。